千葉県にいってきました!〜里山環境改善講座
2015年5月21日木曜日
去る、5月の13日と14日の2日間、千葉県の土気市にある(株)高田造園設計事務所さん(「これからの雑木の庭」の著者 高田宏臣さんが代表)所有の里山空間でおこなわれた、杜の園芸代表 矢野智徳さんのワークショップに参加してきました。冒頭の写真は矢野さんです。
里山環境改善とはなんぞや?とお思いかと存じます。なかなか、ご説明するのは至難の業で、何から話はじめれば良いやら難しいですが、うーんとひねり出してみましょう。
20世紀の後半から今日、コンクリートを使った土木技術によって道路や水路(砂防ダムなどの規模の大きな物もふくめて)が山の中に整備されていきました。その技術は、「自然環境を制御」するという発想で考えられているように思うのです。分厚いコンクリートに鉄筋を入れて、垂直な面で土を真っ向から受け止めるというイメージ。たしかに、理屈からゆうと、コンクリートを分厚くすればする程、鉄筋の本数を増やせば増やす程、「制御」出来る力は増しそうですが、時にそれをも超える自然の圧倒的なパワーはとても人間の技術で制御しきれるものではないことを、毎年のようにまざまざと見せつけられています。
矢野さんはいいます。「自然と対峙するのではなく、寄り添うような方法を見つけて、人間が手を加えた後は、しばらく自然の力にまかせてみる」
「自然の地形には、人間がつくるような,垂直や水平、直線的なラインのものは無い。水や空気が通る道は、緩やかな曲線、螺旋的なラインなんだ(水と空気の彫刻)」と。
直線的な受け止め方をしていると、日頃少しずつ圧力がかかり続け、そのうちおきる大きな力(自然災害)を食い止めることができなくなるが、自然の地形は日常的におこる力を小出しに抜いてゆくことで、いわば、普段からガス抜きをさせることで、一気に集中する力を「かわす」ような形になっているのではないかと理解します。
土木のあり方も、「対峙する」「制御する」という発想にかたよるのではなく、「自然と同じ方向を向く」「水や空気が作り出してゆく方向によりそう」という発想を取り入れてみようというのが、今回の里山環境改善講座やすでにいろんな場所で行われている矢野さんの「大地の再生講座」の基本理念なのかなと、私なりに解釈しているのであります。
それは、土木技術のみならず、これからの人間の生き方にもそのまま重ね合わせる事が出来ると感じています。現に、矢野さんの講座は、土木技術を必要とするような職業(農業、林業、造園)の人達だけではなく、子育て中の若いお母さんがたや自然志向が強い食品関係の仕事をする方など、幅広い参加者がみうけられます。
では、すこしワークショップの様子を写真で見て頂きます。
(文章がながくなっているので、ちょっと読みづらいかもしれません。ここまでの部分がひとつの肝になっていますので、そんなに細かくお知りにならなくてもいいかという方は先に進むことを省略して頂いても大丈夫です!)

ながながとしたブログになってきています。でも、まだまだ言葉足らずでちゃんとかけているのかどうか。(うまいこと伝わってますか〜)
講座の楽しみのひとつは、作業の後には親睦の時間です。
今回の千葉でもそうでしたし、上のかまどの写真の園部でも、みんなで行う作業を終えて自然環境の中でいただく食事は、非常に美味しく楽しいひと時でした。千葉では、高田さんの現在のスタッフさんを中心に、いまは独立され親方になられている佐野さんや松浦さんの会社やお仲間の(株)中央園芸(押田大助代表)所属の若い衆の方々も手伝われて、心のこもったおもてなしを受けました。高田さんご自身も前日は夜遅くまで、飲んでしゃべってのおつきあいをしてくださり(つかれていらっしゃるのに)次の日は朝早くから皆さんそろって朝食の準備をしてくださいました。食材は上の写真にもみえる、自社の畑でとれる無添加、自然農法で収穫された野菜をつかわれています。若い衆は、飲み物もなくなりそうになるかならんかのところで、すかさず次の飲み物をもってきてくれるなど、そのままホテルのボーイになれるでえ!とおもわせられる目配り気配りでした。(すごかったですよ!ほんまに)
以上、かなり解りにくい文章ですがおつき合い頂き有り難うございます。
矢野さんの講座の内容や、そのときどきに発せられる言葉の数々(毎回金言がちりばめられています)と高田さんたちのおもてなし心遣いによって、もう帰りのバス車中ではわれわれ夫婦口をそろえて「また行きたなるなあ」と余韻に浸っておりました。かえってきてもその余韻が続き、しばらく時差ぼけならぬ「千葉ぼけ」がなかなか抜けへん始末です。(最近ようやくふつうの神経になってきました。笑)
矢野さんの園部での講座はちかいところでは5月30,31日にもおこなわれます。
ご興味のある方は是非、主催の高草さんのヘルシーショップらぽ−む (072-749-0550)か、もしくはあまがえるにお尋ねくださいませ!
これからも、時折講座のことをこのあまがえる日誌でも紹介してゆきたいと思っています。まだまだわからんことばかりのなので、感じたことはこちらのブログでもお伝えしていきたいと思っています。おそらく、ちょっと文章が長くなりますが、懲りずにまた宜しければおつき合い下さいませ!
(あまがえる)
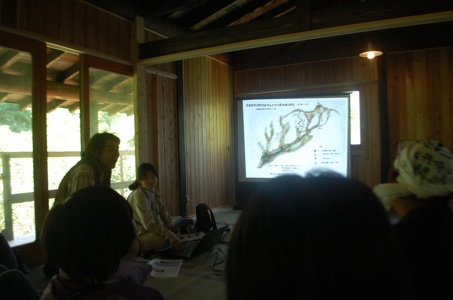
まずは、高田さんたちの手によって建てられた、古材を使った山小屋にての座学です。ちなみにこの山小屋は高田造園設計事務所に所属する、齢80歳を超えた大工の棟梁を中心に建てられました。(居心地のいい空間!よるはこちらで親睦会をしました。)
この座学では、自然環境を大きく分けて四つの次元に分けて分類する所から話がはじまります。大地の環境、生物の環境、水と空気の環境、太陽熱や重力、引力(潮の満ち引きなどもそうですね)などの宇宙的規模の環境です。矢野さんが環境改善の仕事をされる場合も、依頼された場所をこの四つの次元に分類するところからはじまるのだそうです。(細かく分けると八つのファクターに分類できるのですが、割愛させて頂きます。ご了承下さい。)
よく「木を見て森を見ず」という言葉を耳にしますが、ひとつの事柄をみるとき、そのものだけをみるのではなく、取り巻く全体像や因果関係をみることで、理解の巾がひろがることが少なくはないですが、自然の環境におこっていることをとらえる場合も同じで、大地、生物、自然(水と空気)、宇宙エネルギーという四つの次元にまず整理してから、その場所の現状をとらえようという話です。




座学のあとは、フィールドワーク。参加者全員で矢野さんの作業説明の後、実践です。実は、実践編では水の流れなどをスコップで改善してゆくことなどがあり、カメラで写真をとることがそっちのけになってゆきますので、今回もいい写真があまりとれてない!(まことに申し訳ないです)
作業のコンセプトは、写真にも見られるように、「老若男女」のいろんな人達がそれぞれ「やれること」を「やれる範囲でコツコツ行う」という考え方です。矢野さんやスタッフの方々、今回は造園関係者もいますので、重機やチェーンソーなども使ったりする人と、移植ごてやスコップ、草刈り鎌といった手作業組とが一緒になって作業を行います。
昭和の半ば頃までは、各農村ではこのように、村共有の山などの場所を協同作業で維持してゆく「結い」というコミュニティ活動がみられたということも矢野さんはよく例としてつかわれます。
そして、そうゆう作業は、その村々固有の「目の前にある、生(なま)の環境」に応じたものなので、決して今の数値化、一般化された全国どこでもおこなわれるような現在の土木作業ではなく、「そこにあるものをそこに有るようにつかってゆく」作業ではなかったかとおっしゃいます。そして、土木工事という文字の通り、「そこにあるもの」とはそこに有る「土や木(木材)」あるいは石というものが、「そこにあうバランス」でつかわれていたんだとも。
いまでも、田舎の風景で、うまいこと積んでいるなあと思わせる棚田の石積みを見かけることがありますが、きっとあのようなものも、同じようにつくられたんやろうなあとおもわれます。ひょっとしたら、ときには部分的に崩れたりもするんだと思いますが、その都度、「結い」の手によって修理されて使われてきたと思われます。あれが、いまの土木技術では平面的なコンクリートのよう壁にかわるんやとおもうと、風景としても見どころがないと感じますし、小動物の住処にもなりそうな凸凹したような石積みとくらべて、動物たちを寄せ付けない優しくない存在にも見えてきます。実際、川のコンクリート護岸にしても、海の護岸のコンクリートにしても生物が住めない環境なので、最近では凸凹したラインや曲線的なラインにつくりかえるという例もみられます。





上の写真は今回の千葉の講座ではなく、滋賀県の徳昌寺というお寺の内外の環境改善と、現在継続して行われている京都の園部の法京の茅葺きの古民家と圃場(高草俊和さん所有:ダーチャ&ラポーム農場)を含めた環境改善の講座の様子です。
先にふれた四つの環境要素のなかでも、具体的に改善の作業をする場合にしぼられるのは、水と空気の通る道(水脈と気脈という言葉が講座でつかわれます)の改善作業です。
上の写真も、それを行っている様子の写真です。ボクが体験したのは、
1.水が重力によって斜面地の地中を流れ落ちて出る斜面の裾の部分に手を入れるケース
2.実際に斜面地の表面を流れる「小さな流れ」に手を入れるケース
3.山や森林内に重機による掘削で、ダイナミックに水脈と気脈を作ってゆくケースという三つです(三つ目は作業は矢野さんたちの重機によるもの)。
もっと具体的にゆうと、
1では、斜面の裾のラインに沿って、手作業で横溝を作り、何mかおきにその溝の深さよりも深い縦穴(点穴とよばれています)を掘ります。そのあと、溝や穴が雨の際の泥水でうまるスピードを少し緩めるように,「そばに有るような」小さな木の枝などを溝や穴に投入してゆきます。(イメージとしてはビーバーがつくるダムのように。実際ビーバーのダム見たことないですが。)(上のど真ん中の写真を参考にしてくださいませ。)
2の水の流れにおいては、底にたまった細かい泥をすくい上げることからはじまって、あとには全体の流れのスピードが均一になるように「そばにある小さな石や木の枝など」をつかって流れのミニ護岸工事を手作業でする。(ビーバーのダムのように。みたことないけど。もうええか笑)(上の五枚のうち右下の写真が作業後の様子です。)
何度も繰り返してすみませんが、これらの作業は、20人から30人で行う手作業が主の力ですが、おおぜいの人の手作業なので一人一人はとても小さな労力でも2〜3時間で一区切りが付くほどの大きな力となります。先人が各ムラで行っていた「結い」の作業もこのように老若男女のいろんな力が結集して成り立っていたと想像します。バリバリやる若い衆もいれば、炊き出しをする奥さん衆、知恵を出す年配の衆もいれば、周囲を和ましてくれる子供衆もいて、それこそおまつり騒ぎのなかでの作業やったんやろうなあとおもわされるのです。
では、水と空気の流れの改善が、環境改善にどうつながるのか。(ここがポイントですね!)
斜面の裾に横溝をほるのも、水路のドロさらいをするのも空気や水の通りを良くする為の作業です。通りが良くなると、土の中によどみがなくなり、水も空気も耐えず供給されるようになります。土に空気が供給される場所は植物がよく育つようになります。これは深く耕したり、水はけを良くする作業が行われた畑でよく作物がとれることでイメージが出来るかとおもいます。つまり山や林も畑と同様に、植物がよく育つ環境に改善されるということになるといえます。植物がよく育つ土は、土の中の微生物も活発に生きている土でもあります。植物の根と土の中の微生物の共生関係による相乗効果でさらに植物がよく育ち、微生物も小動物もいきやすい環境に変化してゆき、水脈と気脈が改善された土地は緑豊かな状態に変化してゆくと想定されます。(この辺りが造園の仕事にもおおいに応用できる部分!)
植物が元気に育っている土地は、土の中では草木の根が酸素を求めて張り巡らされた状態、いいかえれば土が根によって「しっかりつかまれた」状態となり、小さい視点でみると土砂崩れなどがしにくい土地になり、大きな視点で見るとその山や森林自体が水源となるような豊かな環境に改善されるということなんだと思います。
かなり長くなりましたが、うまく伝えられているでしょうか。(かなり心配です。)
このような植物の根の役割は矢野さんの手法においては、重要な要素といえるようです。
一般の住宅の庭においても、小さな移植ごてから浅い溝や穴を掘るだけでも、お庭の植物の育ち方も改善ができ、それがつながってゆくとひいてはその住宅周辺の地域の環境も改善できるのではということで、参加した造園関係者もこの手法を自分たちの日頃の仕事で実践していくようになってきました。



庇の雨落ちのラインに横溝と点穴を掘り、最後に木の枝を投入して仕上。
田んぼの横の山からの水の流れの整備。ドロさらいのあと、木の枝や石で護岸をします。
石積みの根本にも横溝と点穴をほってゆきます。
寺の敷地内の林。ゆるやかでダイナミックな溝のライン。
道路との境目。斜面の裾部分に横溝と点穴をほってゆきます。
道作りの様子。矢野さんの説明を聞いてからの作業になります。
風の通りを良くする為に、風に揺れる程度の細い枝を剪定します。
流れのドロさらいのあと、木の枝などをつかって仕上。
園部の茅葺きの家のなかのかまど。昼ご飯のカレーを作って下さる高草洋子さんたち。
千葉で最後の昼ご飯。季節外れの台風にも遭わず、いい天気でした。